東京都江戸川区を拠点に、関東一円で耐火被覆工事を手掛けている實川耐工です。
耐火被覆の改修工事を行う時は、元の耐火被覆を撤去し、場合によっては建造物自体にも手を加える必要があります。この際問題になるのが、古い耐火被覆にはアスベスト(石綿)が使われている可能性があるということです。
アスベストは非常に有害な物質なので、建築物等の解体・改修工事を行う時は事前に調査を行い、アスベストが使われているかどうかを確認・報告する必要があります。そこで今回は、アスベストの事前調査のルールや対象工事、罰則、手順などについて詳しく解説します。
■アスベストの事前調査が義務化された背景
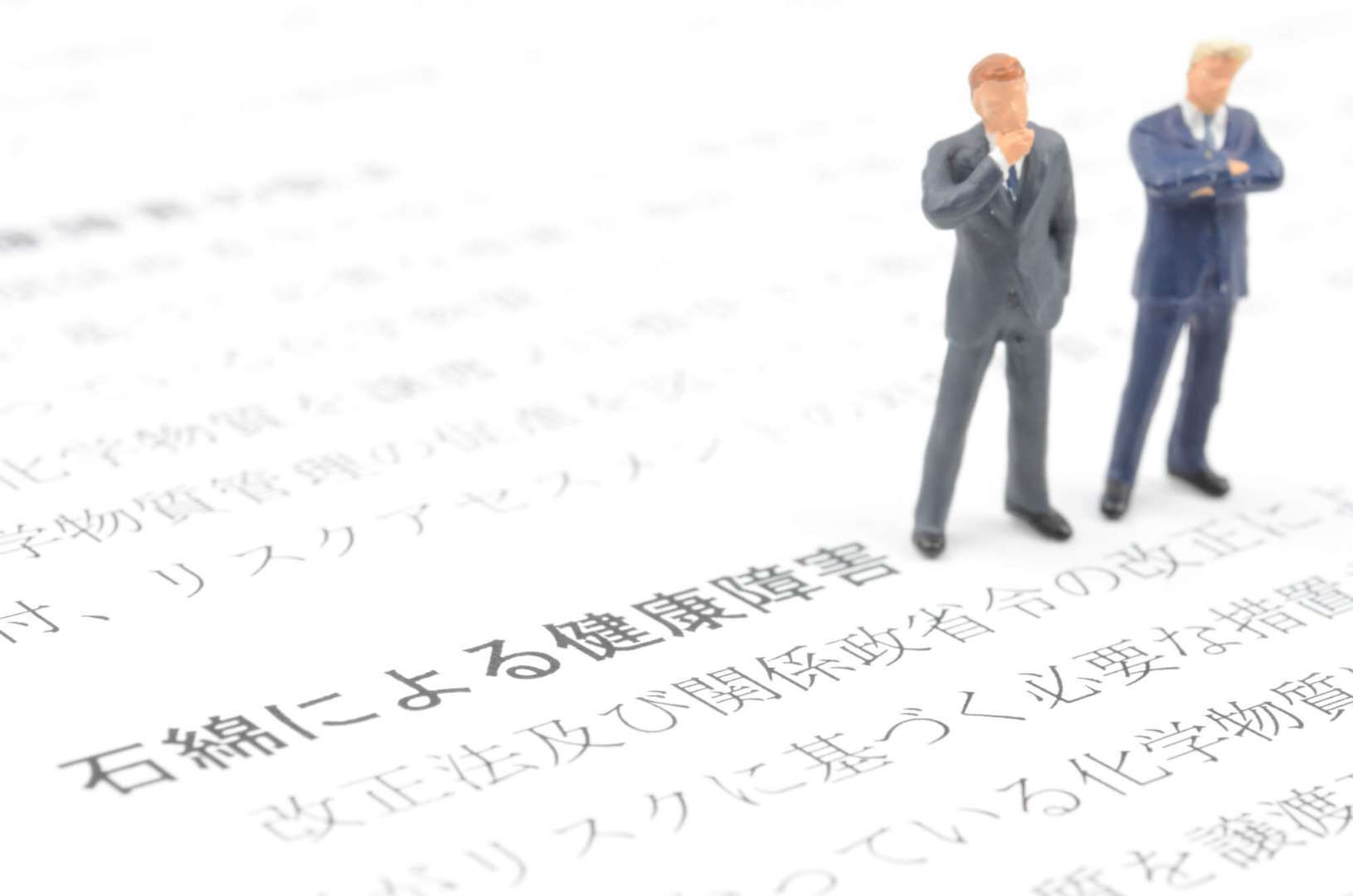
最初に、アスベストの事前調査が義務化された背景について確認しておきましょう。アスベストは繊維状の鉱物で、耐久性や耐摩耗性、耐熱性などに優れ、さまざまな用途で使われてきました。耐火被覆や断熱材など、建築材料としても広く用いられてきた歴史があります。
しかし、1970年代に入ったあたりから、発がん性をはじめとする人体や環境への悪影響が問題視されるようになりました。その結果、徐々に規制が強まり、2006年の労働安全衛生法施行令改正によって、アスベストを含む製品の製造や使用等が全面禁止に。規制が猶予されていた一部の分野でも、代替技術の確立によって2012年には全面禁止になりました。
そのため、最近建てられた建物にアスベストは使用されていませんが、法改正以前に建てられた建物には、アスベストが使用されているケースが少なくありません。何の対策もなしに建物の解体・改修工事を行うと、使用されているアスベストが飛散し、健康被害や環境汚染のリスクが高まります。
実際に、アスベストの健康被害による保険給付は年間1,000件前後と少なくありません。また、2021年5月には、建設現場でのアスベスト被害について国とメーカーの責任を認める最高裁判所の判決が出ています。こういった事情により、アスベストの法規制は年々強化され続けており、事前調査の義務化につながっているのです。
■有資格者によるアスベストの事前調査・報告は義務化されています!
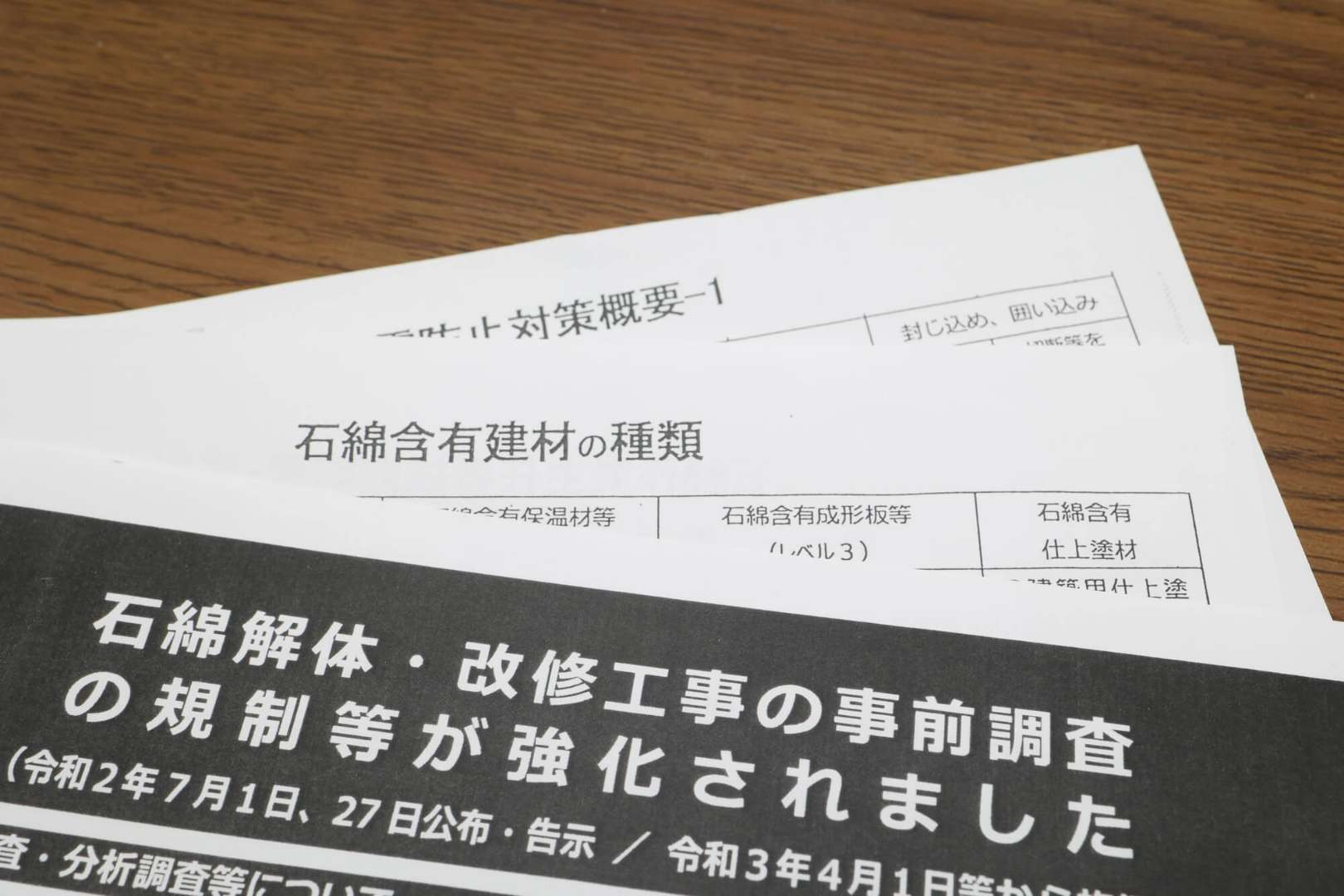
上述した最高裁判所の判決を節目として、アスベストによる被害の拡大を防ぐべく、アスベストの事前調査・報告が義務化されています。その根拠となるのが「改正大気汚染防止法」で、2021年・2022年・2023年の3回にわたって施行されています。
内容を簡単に確認すると、2021年には解体・改修工事を行う際の事前調査方法が法定化され、作業記録の作成・保存が義務付けられました。2022年には、「石綿事前調査結果報告システム」による調査報告が義務化。そして2023年10月1日からは、「建築物石綿含有建材調査者」による調査報告が義務化されています。
建築物石綿含有建材調査者とは、建物の解体・改修工事における、アスベストの使用実態調査の専門知識を証明する国家資格(およびそれを保有する人)です。一戸建て・一般・特定の3つに区分され、一戸建ては住宅(共同住宅の共有部分以外)、一般・特定はすべての建築物を調査対象とすることができます。今のところ、一般と特定の調査区分に違いはありません。
そして調査の結果は、所轄の労働基準監督署および地方公共団体(都道府県等)に提出する必要があります。報告の期限は工事着手日の14日前までで、結果は3年間の保存が義務づけられています。
要するに、国家資格を持つ専門家が着工前に調査を行い、その結果は専用のシステムを通じて役所に報告しなければならないということです。非常に厳しい規制であることがわかります。
■アスベスト調査の対象となる工事

アスベストの事前調査・報告は、原則としてすべての建築物の解体・改修工事が対象となります。単純な解体工事はもちろん、エアコンや電気配線、アンテナ配線、防犯カメラ設置など、「建築物に現存する材料に何らかの変更を加える工事」なら何でも対象です。もちろん、耐火被覆の改修工事も対象となっています。
ただし、比較的小規模な工事の場合は、報告の必要はありません(調査は必要)。具体的には、「床面積80㎡未満の解体工事」「請負金額100万円未満の改修工事」「請負金額100万円未満の工作物の解体・改修工事」なら報告は不要です。(※金額はすべて税込)
また、アスベストの飛散リスクがない工事の場合は、事前調査自体が必要ありません。たとえば、工事の対象が木材・金属・石・ガラス等のみで構成され、アスベストが含まれていないことが明らかで、周囲を損傷させることなく簡単に取り外せる部材。これらを撤去するだけなら、アスベストの飛散リスクはほぼ0なので、調査は不要です。
さらに、釘を打ったり抜いたりといった、ごく簡単な工事でも調査の義務はありません。したがって、工事を行う前には、アスベスト調査が必要なのかどうかをよく確認することが大切です。
■アスベスト調査や報告を怠った場合の罰則
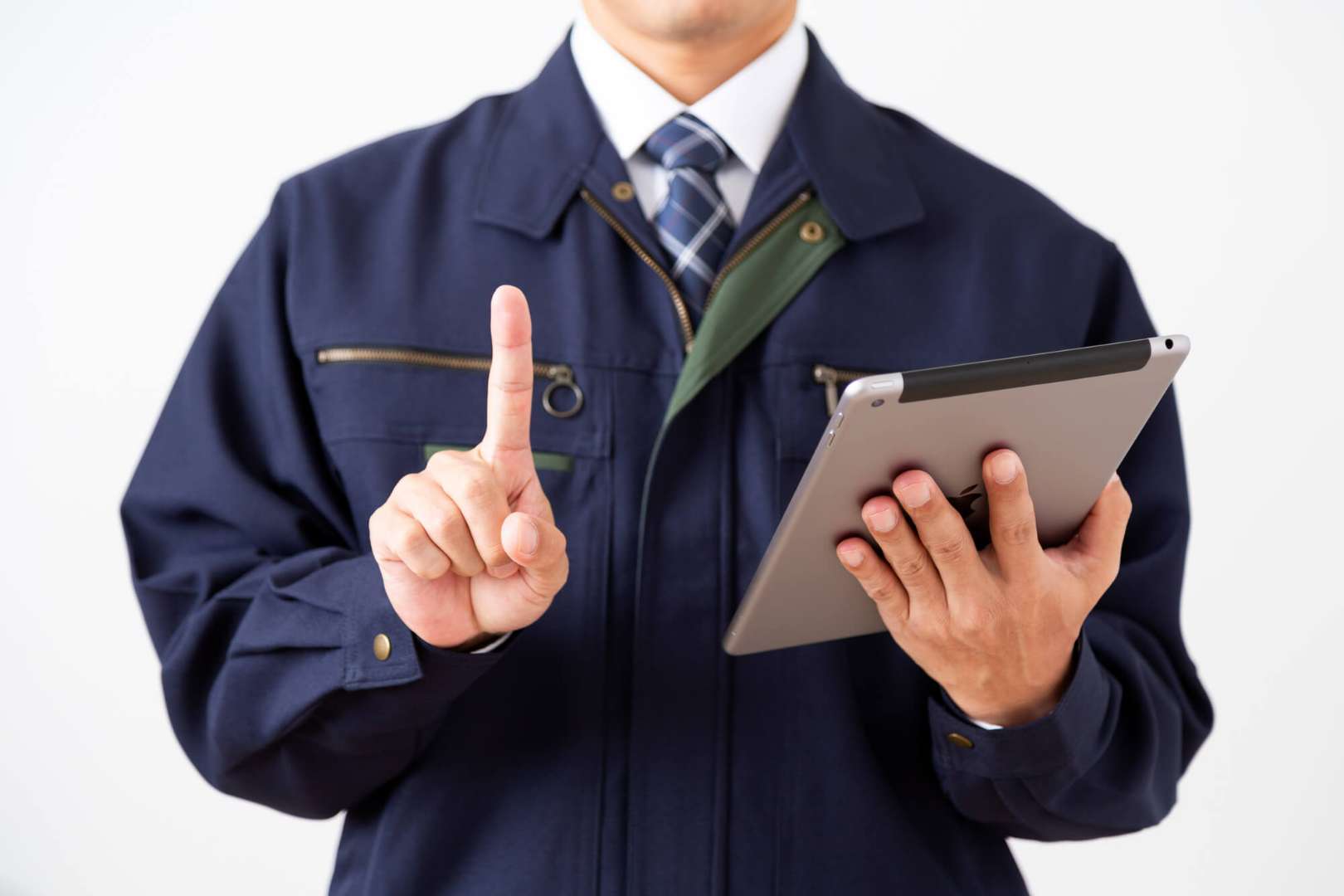
アスベストの事前調査や報告を怠った、あるいは虚偽の報告を行った場合は、大気汚染防止法に基づく罰則が科せられます。また、調査を怠った結果、除去作業中にアスベストを飛散させてしまったり、飛散防止対策を講じずに解体作業を行ったりした場合も同様です。
科される罰則は違反の内容によって異なりますが、主に「除去・調査における義務違反」の場合は、3ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科されます。また、「作業基準適合命令違反」の場合は、6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金が科されるのが基本です。
さらに、アスベスト事前調査を行わずに作業員を解体・改修作業に従事させると、大気汚染防止法とは別に労働安全衛生法(安衛法)違反となり、やはり罰則を科される可能性があります。作業員の安全を守るため、そして企業としての責任を果たすためにも、アスベストの事前調査は必ず実施しなければならないのです。
■アスベスト事前調査~報告の流れ

アスベストの事前調査の義務化は最近になって整備されたルールなので、知ってはいるけれど具体的な流れがわからない……という方も多いと思われます。そこで最後に、アスベスト事前調査の基本的な手順を確認しておきましょう。
①専門業者に依頼
まずは、アスベストの事前調査を行うことができる、経験豊富な専門業者に相談します。前述した通り、建築物石綿含有建材調査者による調査・報告が義務化されているので、有資格者が所属しているかどうかを必ず確認してください。業者に何らかの違反があった場合は、依頼者も責任を問われる可能性があります。
②書面調査
実際に施工した業者に当たるなどして、現場の施工図や設計図書を入手し、現場にアスベストが使われているかどうかをチェックします。アスベストを使ったという直接的な記載がなくても、工事をした時期とアスベストが規制された年代を突き合わせて、使用の有無を推定できることもあります。
③目視確認
書面が見つからない場合や、確認してもアスベストの使用の有無がわからない場合は、目視による現地調査も行います。耐火被覆もそうですが、アスベストは建物のいたるところに使用されているため、目視による確認は非常に大変な作業です。
④分析調査
書面・目視による調査でアスベストの有無が確認できなかった場合は、分析調査を行います。これは、建物からサンプルを採取し、専門の企業に分析を依頼して、アスベストを含んでいるかどうかを調べる調査です。なお、アスベストが含まれているものとみなして、飛散防止措置を講じる場合は、分析調査を省略することができます。
⑤報告書作成
調査結果に基づいて報告書を作成し、所轄の労働基準監督署や地方公共団体に提出します。前述したように、提出期限は着工の14日前まで、報告書の保管期間は3年間です。報告は専用のシステムを通し、24時間オンラインで行うことができます。
■まとめ

アスベストは非常に有害な物質であり、その飛散は徹底的に防ぐ必要があります。解体・改修工事を行う際のアスベスト事前調査は義務化されているため、どのような建物でも原則として実施しなければなりません。
違反した場合は作業員が危険にさらされ、会社が罰則を受けるリスクがありますから、法律に則って確実に調査を実施することが大切です。特に耐火被覆の改修工事を行う場合は、アスベストの事前調査や撤去もあわせて行える業者に相談するといいでしょう。
■アスベスト除去から耐火被覆工事まで、全部實川耐工にお任せください!

實川耐工は、耐火被覆工事の専門業者です。迅速・柔軟・丁寧な施工により、多くのお客様からの支持をいただいてきました。圧倒的なスピードと仕上がりの美しさ、臨機応変な対応力により、幅広いご要望に対応できるのが強みです。新築はもちろん改修工事にも対応し、施工後のメンテナンスもしっかりと行います。
さらに、アスベストの事前調査・除去から耐火被覆工事までワンストップで行えるため、複数の業者に依頼する場合に比べて手間がかからず、コストも抑えることが可能です。耐火被覆工事をご検討の際は、ぜひお気軽にご相談ください。
▼関連記事▼
》耐火被覆工事とは? 目的や必要性、ルールを解説!
》耐火被覆の工法の種類とそれぞれの特徴を解説!
》火災による建物の倒壊リスクを減らそう!耐火被覆工事のメリット・デメリットを詳しく解説
》準耐火建築物とは?耐火建築物との違いや耐火被覆の重要性など耐火被覆のプロがわかりやすく解説!
》ロックウールとアスベストの見分け方は?それぞれの特徴やよく使用されている場所を紹介!


